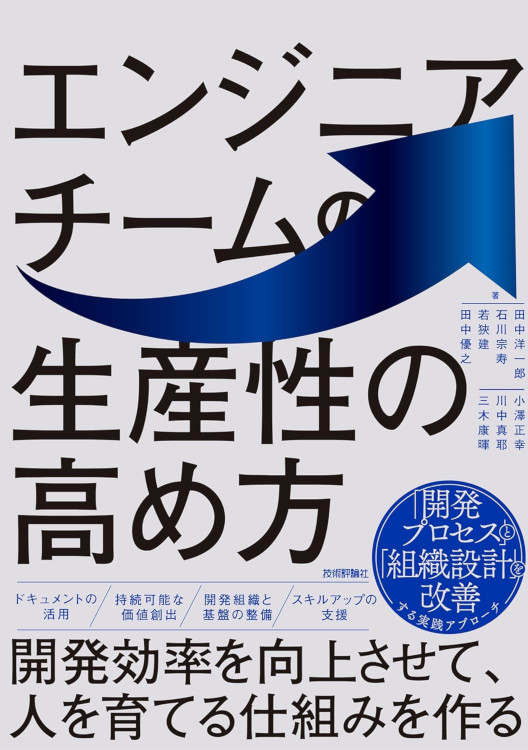Design Overview "Conversational UI and Why It Matters"を日本語訳しました
Google AssistantへのアプリによるUIの提供は、会話型になります。つまり、GUIのような「画面の操作」ではないので、アプリの開発者はどのように会話を組み立てれば良いのか、悩むはずです。Actions on Googleのドキュメントでは、アプリのデザインの概要として、Conversational UI and Why It Mattersが掲載されています。以下はその日本語訳になります。原文でも難しめの記載になってるため、日本語訳も微妙な感じになってますが、キーワードだけでも...